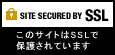【商品名】 「田中松太郎」翁自筆日記
【執筆年】 昭和20〜22年
【状態】 両見返しノド少イタミ、経年相応の劣化有
【備考・コメント】
B6変判、420P程、ハード装、ペン書。
■執筆者の田中(旧姓:飯森)松太郎氏は、文久3年8月3日越中国婦負郡(現・富山県富山市)に生まれた。
師事した日下部鳴鶴の息子・田中美代二から写真を学び、美代二が急逝した後に彼の妻と結婚し田中家を継ぐ。欧州に渡りウィーン王立写真学校で三色網版製版術を修得し、大正4年に田中半七製版所(千代田区)を開業した。
新技術の改良や後進の教化に努めた氏は昭和16年に東京日日新聞より『印刷功労賞』を受賞し、「写真製版界の父」や「本邦美術印刷の功労者」と称えられている。また、「木曜会」「パンの会」にも所属し、多くの芸術家たちと親交があった。
■氏は昭和24年に86歳で逝去したが、本品は最晩年(82〜84歳)にあたる群馬県勢多郡新里村疎開時代の日記で、昭和20年10月1日〜昭和22年8月31日まで、数日を除き毎日綴られている。家族は先妻亡き後に再婚した妻の「紀伊」、紀伊の養子で東京写真工業専門学校へ通う「達也」、氏の実子と思しき「元吉」(病弱で昭和22年2月23日に慢性腹膜炎により逝去)で、ほかに使用人らしき女性と犬・猫・兔と暮らしている。
慢性的に食料や物資が不足し、停電が頻繁に起こるなど終戦直後の混乱下ではあるものの、ほぼ隠居の身である松太郎翁は至ってマイペースだ。朝起きてラジオを聴き、郵便物の受発信録を書き付け、創作や読書をし、身の回りの修繕や整理を行い、家族らと近所の鶴ケ谷鉱泉へ入浴に出かけるなど、友人や知人の往来も多く程良く活気のある日々を過ごしている。
自身の事や世間の出来事(近衛文麿服毒自殺・天皇マッカーサー第二回会見・ビキニ環礁核試験・二.一ゼネスト禁止令・新憲法施行等々)は概ね淡々と記しているが、家族に関しては些細な出来事でも丁寧に記録している。
■内容の極一例
石井鶴三より農婦を描写した葉書が届く(昭20年10月27日)、大晦日の晩に牛肉のすき焼きを食し「贅沢なり」(同年12月31日)、杉浦翠子より『日の黒点』200部限定版が届く(昭21年1月20日)、強制疎開で飯田町に移転した半七工場の復興計画について来訪した米屋本田両氏と詳細を話し合う(同年2月21日)、岩波茂雄死去の電報を受けて驚愕し直ちに仏壇に燈明心経供養す(同年4月26日)、達也が菓子箱を利用して製作した「電気パン焼器」の試作パンを客人に供す(同年5月28日)、和田秀豊永眠の知らせが届き「嘆やまず」(同年8月22日)、法師温泉へ旅行に出掛け長寿館等に宿泊(同年8月24-31日)、来訪した松野自得と「マカオエコスマージュ」を鑑賞し黒石一個を硯とせんことをすすめ赤楽茶碗を贈る(同年9月1日)、食事をめぐって勃発した元吉と紀伊の親子喧嘩を「浅ましい」と嘆く(昭22年1月15日)、半七工場製の新憲法発布の写真版を掲載した『不死鳥』第9号が杉浦非水・翠子夫妻より届く(昭22年1月16日)、亡くなった元吉の遺骨を東京・豪徳寺へ納めた帰途に半七芝浦工場へ立ち寄る(同年3月4・5日)、半七写真製版印刷所に関する一切を田村寅之助に委任す(同年3月15日)等々
★郵便物の受発信録には、岩波茂雄、和田秀豊、和田英作、杉浦非水、杉浦翠子、濱田庄司、沖野岩三郎、久米福衛、古島一雄、宝来市松、有島生馬、村上福三郎(木村哲二)、酒井杏之助、高島米峰、津軽照子、石井柏亭、小杉放庵、安田靫彦、土岐善麿、福原信三、津田青楓、川島理一郎ほか多数の名が記されている。
日記の巻頭に自身の蔵書票糊付、また、受領証・領収証・電報・記事切抜などが所々に貼り込まれている。